| 井上靖 『本覚坊遺文』 | |||
|
ー“無”と書いた軸を掛けても、何もなくなりません。“死”と書いた軸の場合は、何もかもなくなる。“無”ではなくならん。“死”ではなくなる! 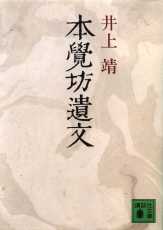 謎に包まれた千利休の賜死事件について、利休最後の弟子本覚坊の手記をもとに茶人利休の心を探っていく。 謎に包まれた千利休の賜死事件について、利休最後の弟子本覚坊の手記をもとに茶人利休の心を探っていく。歴史を題材にした井上靖の小説はどうも大味なものが多い、そんな先入観を持っていたのだが(主には『蒼き狼』や『風林火山』『敦煌』などの作品を読んだ感想である)、この作品ではそんな予想を完全に裏切られた。実に素晴らしい作品である。 なんだかんだと解説をする以前にとにかく面白い。茶道の創始者は利休だろうと漠然と思っていたくらい「茶の湯」について知識のない自分にとって、ところどころ分かりにくい部分があったのだが、そのようなことについて全く関係なく、実に面白かった。 第5章までは利休について、特にその賜死事件についての東陽坊、古田織部、織田有楽斉などとの対話で構成されている。そのなかでは利休の死についてだけではなく、茶の湯に関わるまわりの人々のことについても話が及んでいき、まるで闇の中を進んでいるかのようである。ところが終章においてそこまでほとんど聞き役に徹していた本覚坊の利休観が示されるにおいて、それまでの会話が一気につながりを持ち、そこまでの道のりが見事に見渡せるようになるのである。まるで推理小説のような見事な構成であると思う。無論そこで提示される利休自刃の心についてはあくまで本覚坊=井上靖の一つの解に過ぎないのであるが、そんなことは問題ではなく、とにかく感動を覚えてしまう。そしてまたそこまでの展開を考えても、十分に説得力のあるラストだと思う。 この小説は技巧的な面でも結構面白いところが多い(こういう技巧的な作り方は井上靖の小説には珍しいようにも思う。単に今まで気づいていなかっただけかもしれないが)。とはいえそういうところはやはり枝葉、この本には小説としての面白さが十分に入っている。ぜひそれを味わってもらいたい、と思う。 余談だが、この小説は確か映画化されているはずである。これだけ見事な文章芸術を、どう映画で表現しようとしたのか、そこら辺もちょっと興味がある。 ー利休どのはたくさん武人の死に立ち合っている。どのくらいの武人が、利休どのの点てる茶を飲んで、それから合戦に向かったことか。そして討死したことか。あれだけたくさんの非業の死に立ち合っていたら、義理にも畳の上では死ねぬだろう。そうじゃないか。 | |||
|
|